水の都大阪再生プロジェクト

マリンスポーツを体験しながら海上のゴミ拾いをしよう!
【水の都と呼ばれていた 大阪を取り戻そう!】
9月28日に大阪ふれあいの水辺(桜ノ宮ビーチ)で大阪のトヨタソーシャルフェスを開催し、約80名にご参加いただきました。当日は風が少し吹いていて涼しさを感じるちょうどいい気候で、開会式の時間まで皆さん思い思いの時間を過ごされていました。

【SUP体験! ビーチヨガにも挑戦!】
開会式が終わると2班に分かれてマリンスポーツ体験とビーチクリーンが始まりました。今回体験いただいたマリンスポーツはSUP(スタンドアップパドルボード)です。1人乗りと6人乗りのSUPに学生やファミリーがチャレンジ。膝立ちから徐々にコツをつかんで立ち上がり、水面をスイスイと進んでいました。SUP体験の合間にはビーチヨガ体験も行い、いろいろなポーズにチャレンジされていました。

【学生団体による ビーチクリーンと 分別活動!】
ビーチクリーンでは学生団体NAMIMATIの協力のもと、会場周辺のゴミ拾いと分別を行いました。参加者からは「きれいに見える街でも思ったよりゴミが落ちていて、日ごろの生活から気を付けたいと思った。」という声もいただきました。意識の高い学生の方が多く、大阪がまた水の都と呼ばれるようになるのもそう遠くない未来かもしれませんね!

【50年後、100年後も 魅力あふれる大阪へ】
今回の活動を通して水辺のアクティビティの魅力や自然の魅力など、いろいろと感じていただけたと思いますが、そうした体験ができる環境を自分たちで守っていくことの大切さも感じていただけたのではないかと思います。こうした活動を広げていくことで50年先、100年先もいろいろな生き物が暮らすことのできる魅力あふれる自然を残していきたいと思います。

◆主 催:公益財団法人マリンスポーツ財団
◆協 力:産経新聞大阪本社
自然とふれあい親しむことで、自然の素晴らしさと環境保全の大切さを学ぶ

マリンスポーツを体験しながら、環境問題について考えよう!
【水の都と呼ばれていた 大阪を取り戻そう!】
マイクロプラスチックゴミの問題や自然の大切さについて考える大阪府のFESを10月28日に大阪府立青少年海洋センターで開催し、約80名にご参加頂きました。当日は少し風があるものの天気は良く、参加者は気持ちよさそうに海を眺めながら開会を待たれていました。

【みんなで力を合わせて 手漕ぎボート(カッター)体験!】
開会式が終わると2班に分かれてマリンスポーツ体験と海辺のゴミ拾いが始まりました。今回体験いただいたマリンスポーツはカッターと呼ばれる手漕ぎボートです。20人ほど乗ることができるカッターに乗船した参加者はスタッフからオールの漕ぎ方や掛け声を教わり、いざ海上へ。1、2、1、2と掛け声で息を合わせながらオールを漕いで海上をすいすいと走り回り、大人も子どもも楽しまれていました。

【海のいろいろなお話と 海辺のゴミ拾い】
カッター体験だけではなく、参加者には海辺のゴミ拾いもしていただきました。ゴミ拾いの合間には大阪湾で環境活動に取り組まれている「チーム☆ガサ」の鍋島先生からマイクロプラスチックゴミのお話や大阪湾に迷い込んだクジラのヨドちゃん、岬町に棲むイルカの親子のお話もしていただき、環境のことや生き物のことについて自分にできることをあらためて考えるきっかけになったと思います。

【50年後、100年後も 魅力あふれる海へ】
今回の活動を通して海の魅力や自然の魅力など、いろいろと感じていただけたと思いますが、そうした環境をこれからも残していくために、日々の生活の中でできることがたくさんあることも知っていただけたのではないでしょうか。こうした活動を広げていくことで50年先、100年先もいろいろな生き物が暮らすことのできる魅力あふれる海を残していきたいと思います。

◆主 催:特定非営利活動法人 ナック
◆協 力:産経新聞大阪本社
自然とふれあい親しむことで、自然の素晴らしさと環境保全の大切さを学ぶ

マリンスポーツを体験しながら海上のゴミ拾いをしよう!
【TSF!!2022】大阪開催
【水の都と呼ばれていた 大阪を取り戻そう!】
マイクロプラスチックゴミの問題や自然の大切さについて考える大阪府のFESを10月9日に現地とオンライン配信のハイブリット形式で開催し、合計約80名の方にご参加いただきました。当日は運営団体の広報活動などに取り組まれているMarisガールの高橋さんのMCでイベントが進行。現地もオンラインもイベント終了まで盛り上げていただきました。

マリンスポーツ体験! 海のゴミを拾おう!
開会式が終わると、現地では早速マリンスポーツ体験と海ゴミの回収が始まりました。 SUPやエンジン付きのボートなど4種類のマリンスポーツの機材に海ゴミ回収用の網を設置。自動的に海ゴミを回収できる体制を整え、参加者は希望したマリンスポーツを体験しながら海ゴミを回収していきました。オンライン視聴者には現地参加者が体験した活動内容の事前撮影動画をご視聴いただきました。

【マイクロ プラスチックゴミを 見つけよう!】
マリンスポーツ体験終了後、参加者は網の中に入った海ゴミの中から5ミリメートル以下のプラスチックゴミ、通称マイクロプラスチックゴミを探していきます。マイクロプラスチックゴミは色や形も様々で、もともとどんな用途で使われていた物が、どうして海に流れ着き、ここまで小さなゴミになったのか。皆考えても答えは出ないようでした。

【SDGsの14番 海ゴミの問題を学び 「海の豊かさを守ろう」】
マイクロプラスチックゴミを探し終えた後は、化学の先生として多岐にわたって活動されている「さかさパンダ先生」による海ゴミについての講義をオンライン参加者も含めてご視聴いただきました。このままだと海ゴミの量が海の生き物より多くなってしまう可能性があること。海ゴミをエサと間違って食べてしまった魚を、私たちが食べている可能性があることなど、いろいろなことを学びました。今回の活動を通して、海ゴミの問題が非常に身近な問題であることに気づいていただけたのではないかと思います。

◆主 催:二色の浜公園管理連合会(運営主管 公益財団法人マリンスポーツ財団)
◆協 力:産経新聞大阪本社
自然とふれあい親しむことで、自然の素晴らしさと環境保全の大切さを学ぶ

柏原市役所の新庁舎でSDGsと大和川流域の取り組みを学ぼう!
【TSF!!2021】大阪開催
【柏原市役所からオンライン配信で開催!】
SDGsについて学び、水上自転車の動画を視聴する大阪府のTOYOTA SOCIAL FES!!を11月13日に柏原市役所の新庁舎からオンライン配信で開催しました。この日は天気もよく、現地開催できないのが残念でしたが、それでもたくさんの方にご視聴いただきました。
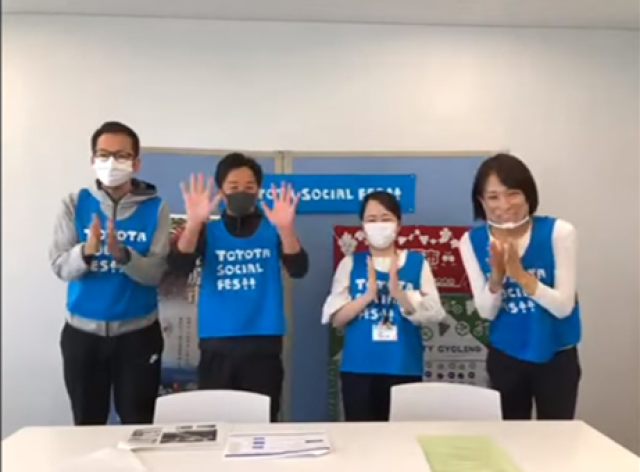
【SDGsや柏原市について知りました!】
当日のプログラムでは、大阪府の水谷さんからSDGsについての簡単なクイズや海ごみとして問題になっているマイクロプラスチックごみについてなどお話しいただき、柏原市の小林さん・松田さんから柏原市の魅力や大和川における取り組みについて動画や資料を交えてご紹介いただきました。また、現地開催の場合に予定していた大和川で水上自転車に乗る体験を事前に撮影した動画も見ていただきました。講義や動画を通して自然を守っていくことの大切さや大和川が時間をかけて少しずつきれいになっていることも感じていただけたのではないでしょうか。
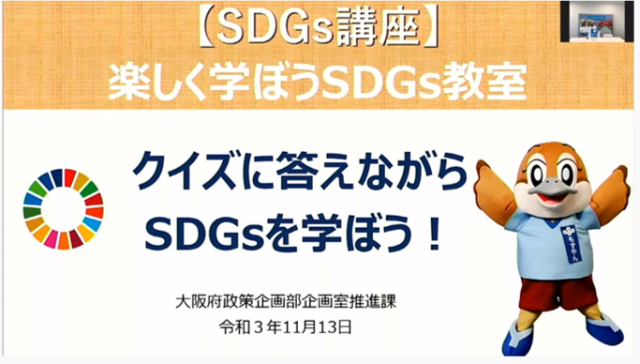
【豊かな自然を次世代につないでいこう!】
今回は実際に体験いただくことは叶いませんでしたが、自然にふれあう機会はこれからもたくさんあるでしょう。皆さんにはそういった体験を目一杯楽しむとともに、こうした自然をこれからも守っていかなければならないという思いを持っていただけたらと思っています。その第一歩として、SDGsの講義で学んだことの中から自分にもできることを何か一つでもいいので実際に自分の生活の中に取り入れてみましょう!

【できることから取り組んでみよう!】
SDGsというと少し難しく感じるかもしれません。しかし、今回の講義を通して、皆さんが生活の中で取り組めることも意外とたくさんあることを知っていただけたと思います。食べ残しをしないようにする。服は捨てずに、なるべくリサイクルする。詰め替え可能な商品を買う。使っていない部屋の電気や家電の電源はこまめに消す、節水を心がけるなど。こういったこともすべてSDGsにつながっています。一人一人の心がけや行動の一つ一つが地球の環境につながっていることを忘れないようにする、それが大切なのです。

【オンライン開催の可能性】
現地開催であれば自然の中で楽しい体験ができればと考えておりましたが、オンライン開催ではどういった内容にするのか、実は開催直前までドタバタしていました。しかし現地参加ではなかなか来られないような遠方の方にも参加していただき、自然の魅力や自然の大切さをより広く伝えられるという点でオンライン開催の可能性も感じました。来年は自粛生活が収束し、現地での開催+オンラインでより多くの方に参加いただけるイベントにできればと思います。

【水の都大阪大阪活性化プロジェクト】
今回のTOYOTA SOCIAL FES!!は水の都大阪活性化プロジェクトというテーマを掲げていました。プログラムを通して自然を守ることの大切さや自然に親しむことの楽しさを感じていただくことで参加者のみなさんには日々の暮らしの中で自然環境保護に対して意識を持つようになっていただけたのではないかと思います。その意識を周囲にも少しずつ広げていくことができれば、かつて水の都と呼ばれた大阪の姿に近づいていくのではないでしょうか。参加してくださったみなさん、ありがとうございました!








