ドラゴンカヌーで海学びプロジェクト

横浪半島から高知の豊かな自然と海の生き物について楽しく学ぼう
【ドラゴンカヌーを通じて 横浪半島の豊かな自然と 生き物について学ぼう】
横浪半島は、須崎市と土佐市にまたがる美しい地域で、特にその複雑で変化に富んだリアス海岸が特徴です。この地域は県立自然公園に指定されており、豊かな自然環境が広がっています。しかし、地球温暖化の影響は日本全体に及んでおり、高知県も例外ではありません。特に海水温の上昇は、水産資源に大きな影響を与えています。これにより、漁業や海洋生物の生態系が変化し、資源の確保が難しくなってきています。まずは自分たちが住む海域の環境を知るため、ドラゴンカヌーで海をツーリングしながら、豊かな自然と海の生き物について学びを深めてもらいました。

【横浪半島周辺に住む 海の生き物は? ドラゴンカヌーで 海を間近で感じよう!】
7月20日(土)、横浪半島の内湾に位置し、波も風も穏やかな須崎市の浦ノ内湾にある「よこなみアリーナ」に子どもから大人まで約100人が集まりました。初めに高知大学のサークル「かめイズム」の水本悠斗さんに研究しているウミガメの生態や横浪半島周辺の海の生き物について講演してもらいました。水本さんは、横浪半島に住んでいる生き物についてクイズを交えながら紹介し、地球温暖化や環境汚染が海にどういった影響を与えるのかについて話しました。私たちが海の生き物を守るためにできる環境保全活動の大切さを学ぶことができました。続いてドラゴンカヌーをするために海へ。当日は梅雨明けの翌日で強い日差しが照り付け夏の到来を感じさせる暑さの中、参加者はまずドラゴンカヌーで浦ノ内湾をツーリング。海の中の生き物や横浪半島の自然を身近に感じ、環境保全の意義を考えることができました。その後4チームに分かれドラゴンカヌーでの競争を実施。各チームが掛け声を出し合いオールをこぎ、白熱したレースを楽しみました。

【横浪半島の海と 周囲の自然を体験、 今後の行動につなげよう】
今回の活動を通じて参加者からは、「地球温暖化が進行していることが分かった」「プラスチックごみを海に出さないことが重要だと知った」などの感想が寄せられました。海と私たちの生活は密接に関わっており、日々の行動が海の環境に影響を与えることを理解することが重要です。例えば、プラスチックごみの削減など、日常生活でできる小さな取り組みが、環境への負担を軽減する一歩になります。環境への影響を減らすためには、一人一人の行動が必要です。ドラゴンカヌーのように一人の力は小さくとも、全員が協力することで大きな力となります。今後も豊かな自然を守る意識を持ち、この行動を続けていく意義を再認識しました。

◆主 催:高知新聞社
◆共 催:すさきスポーツクラブ
◆後 援:須崎市
流れ着いた漂流物からのメッセージを考え、地球や自然のつながりを学ぼう

砂浜美術館に流れ着いた漂流物を学んで集めてクラフトを楽しもう
【漂流物から 環境問題と自然との つながりを学ぼう】
黒潮町の入野海岸は、全長約4キロの美しい遠浅の海岸線が続く、日本の渚百選にも選ばれた海岸です。この美しい海岸にも、さまざまな漂流物が流れ着きます。流木、クジラの骨、近年問題になっている海洋マイクロプラスチックもその一つです。高知県の豊かな自然を守るためにTOYOTA SOCIAL FES‼では、砂浜美術館と連携し、入野海岸に流れ着く漂流物から海の環境問題や自然とのつながりを学びつつ、拾った漂流物でクラフト作りに挑戦してもらいました。

【流れ着く漂流物 その種類と経緯は? 入野海岸で拾った 漂流物でクラフト】
10月14日(土)、入野海岸を見下ろす位置にある「ふるさと総合センター」に子どもから大人まで約80人が集まりました。初めにNPO砂浜美術館の大迫綾美さんに入野海岸そのものを美術館とする考え方やそこに流れ着く漂流物の経緯と種類について講演してもらいました。大迫さんは、「漂流物はロマンを感じるものから環境問題を考えさせるものなどさまざまなメッセージが隠れていて、地球全体を映し出す鏡のようになっている」と話し、実際に所蔵している漂流物も紹介。参加者は環境問題への意識を高めました。

続いて実際に漂流物を拾いに海岸へ。前日に日本付近を台風が通過した影響もあり、多数の漂流物が流れ着いていました。参加者は多種多様な漂流物に驚きながらも、流れ着いた経緯を考えながらビーチコーミングを行いました。そして最後に、拾ってきた漂流物を使ったクラフト体験です。参加者は創意工夫を凝らして自分だけのオブジェやフォトフレームを作成。出来上がったものを互いに見せ合い、クラフトを存分に楽しみました。

【美しい海を 次世代につなぐために】
今回のプログラムでは、砂浜で漂流物を拾い、その漂流物をクラフトに使うことで砂浜にどのような経緯でどういった漂流物が流れ着いているかを深く考えることができました。海に面した高知県では、海からさまざまな恩恵を受けています。プログラムを通じて体験したことを日々の生活に置き換えて行動する、それが美しい海を次世代につなぐために今できることだと感じる機会になりました。

◆主 催:高知新聞社
◆共 催:NPO砂浜美術館
◆後 援:黒潮町
森を歩き多様な植生や季節の草花に触れ、豊かな自然を暮らしに取り入れてみよう

植物学者・牧野富太郎にゆかりのある土佐山で里山クラフトを楽しもう!
【TSF!!2022】高知開催
【土佐山の自然に学ぶ 身近な「山の恵み」】
森林率全国一を誇る高知県。緑豊かな自然は高知の財産である一方、手入れが十分に行き届かないと、豪雨発生時には土砂崩れ等、大きな災害を引き起こす危険をはらんでいます。
山の環境を知ることは川や海、周辺の生態系を守る第一歩となり、私たちの暮らす高知を守ることに直結します。本年度は、土佐山を拠点に活動する「土佐山アカデミー」と連携し、土佐山の里山について学びつつ、事前に採取した植物でクラフト作りに挑戦しました。

【里山の歴史や植物解説の スライドに興味津々】
開催当日は抜けるような青空、そして山間の少し冷んやりした空気の下「土佐山夢産地パーク交流館かわせみ」でTOYOTA SOCIAL FES!!2022in高知がスタート。現地には約70人、オンライン視聴でも多数が参加。第1部は高知大学名誉教授の石川慎吾先生に土佐山など里山の植生について講演してもらいました。生涯で40万枚の標本を作製し、約1500種類もの植物に命名した牧野富太郎博士と土佐山との関わり合いに触れる場面もあり、参加者は興味津々。実際に名付けた植物を見て「普段見慣れた植物の名前の由来が分かってとても身近になった」とうなずいていました。

【学んだ植物を使って クリスマススワッグ作り!】
続いて第2部は事前に土佐山で採取した植物を使ってクリスマススワッグを作りました。講師はフラワーアレンジメント教室などを開催されている、SOU flowerの田井東結さん。現地の方は会場内に準備された数十種類の植物を、オンライン視聴の方は事前に送付したキットの植物を組み合わせて、各々オリジナルスワッグを制作。講師のアドバイスに耳を傾けながら、制作作業に集中する参加者の皆さん。試行錯誤しながらも完成にこぎつけた参加者からは「沢山の植物で色鮮やかなスワッグが作れてうれしい」と満面の笑み。友達連れ、ご家族連れ、画面越し、皆それぞれが〝土佐山の恵み〟を使ったクラフトを存分に楽しみました。

【土佐山スワッグを通じて より良い環境を未来に】
今回のプログラムで使用した種類豊富な植物は、土佐山の自然が長い時間をかけて育んできた「恵み」であることを学びました。この豊かな自然を守るために私たちができること、環境保全の重要性を改めて認識する機会となりました。

◆主 催:高知新聞社
◆共 催:特定非営利活動法人土佐山アカデミー
◆後 援:高知市
森を守り木を育てることで、多様な生物が暮らす高知の豊かな自然を未来に残そう!

甫喜ヶ峰で体感!森の大切さを学び、間伐や木工クラフトを楽しもう!
【TSF!!2021】高知開催
【高知・甫喜ケ峰森林公園からオンライン配信】
高知県でのTOYOTA SOCIAL FES!!は新型コロナウイルスの感染拡大に配慮し、甫喜ケ峰森林公園からオンライン配信での開催となりました。10月23日の配信当日は、全国各地から80名以上の方々が参加してくださり、森林の大切さについて学びました!

【オンラインでも楽しめるプログラムに】
当日は高知県山林協会の協力の下、事前に撮影した間伐シーンなどを交えた座学を配信し、森林の働きや、その森林を守るためにどのような活動がされているのか、またどのような資源として活用されているのかを学びました。その後、参加者の方々に事前送付していた製作キットを活用し、木工クラフトやコケ玉作りをオンラインで一緒に体験。この木工クラフトに使用した木材は、実際に甫喜ヶ峰の間伐材を活用しました。

【当たり前のようで当たり前でない森の恩恵】
日本の国土の約2/3は森林が占めていると言われています。高知県はその中でも特に森林が占める割合が高い県で、実に84%が森林に覆われた県なのです。しかしその森も、きちんと整備し、手入れをしていかなければ、その役割を十分に果たすことができません。間伐を行い、太くしっかりとした木を育てることで、豊かな土壌が保全され、森が育っていくのです。私たちの暮らしを支える資源として、森から受けている恩恵というのは、実はすごく大きいのです。
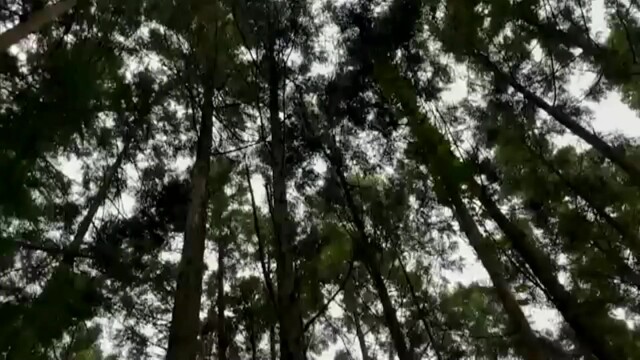
【クラフトとコケ玉作りで学ぶ自然の魅力】
植物の根っこを粘土質の土で包み、その周りにコケ植物を巻き付けた「コケ玉」。苗木、土、コケのすべてが甫喜ヶ峰のもの。木の実や丸太などクラフトの材料も同じ甫喜ヶ峰の自然の中で採取した自然の一部です。自然に触れて楽しみながら学ぶことで、興味や関心、自然を大切にする心を育みました。植物も、そのあたりに生えているからといって勝手に採取してはいいものではありません。ちゃんと持ち主がいて、大切に育てているのかも。クラフトやコケ玉の作り方だけでなく、そんな気遣いについても学びました。

【プリウスPHVを使った給電】
今回、クラフトの際のグルーガンへの給電で活躍したのが、トヨタ自動車のプリウスPHV。実際にプリウスPHVから給電しつつ、グルーガンを使用する様子を配信したほか、木材をカットするためのスライドソーへの給電も実演配信し、その汎用性を発揮しました。コロナ禍で実際にチェーンソーを使用して間伐体験を実施してもらえなかったのは心残りでしたが、また機会があれば是非、実際の自然の中で体験していただきたいです。

【自然について考えるきっかけに】
オンラインイベントの最後には、TOYOTA SOCIAL FES!!実施を記念し、植樹を行いました。こうした木々一本一本が、空気を綺麗にし、水を蓄え、森を豊かにし、我々の生活を支えています。今回の学習をきっかけに、森林の重要性について少しでも理解が進み、一人でも多くの皆さまの心に、自然を大切に考える気持ちが芽生えるといいなと思います。小さな事でも、みんながやれば大きな前進となるはずです。ご参加いただきました皆さま、どうもありがとうございました!








